
IP(知的財産)という言葉は、ゲーム業界ではキャラクターや世界観などの“資産”としてよく使われますが、本来は著作権や商標、特許といった法律用語に由来するものです。 現場ではビジネス的な意味合いで広く使われていますが、扱いを誤ると契約や権利関係でトラブルになりかねません。 だからこそ、感覚的な理解だけで済ませず、法律面からもIPをしっかり捉える姿勢が実務ではとても大切になります。
IPとは?ゲームやエンタメ業界で使われる意味を解説

近年、ゲーム業界やエンタメ業界で頻繁に使われるようになった「IP(アイピー)」という言葉。「人気IPとのコラボ」「新規IPを立ち上げ」など、マーケティングや企画の現場でよく見かける用語です。
この「IP」は「知的財産(Intellectual Property)」の略で、作品やキャラクター、ストーリーなど創作活動から生まれる価値ある“権利”や“コンテンツ”のことを指します。つまり、ゲームで言えば「ポケットモンスター(以下、「ポケモン」)」「ドラゴンクエスト」「モンスターハンター」などのブランドそのものがIPと呼ばれる存在です。

IP(知的財産)は、作品やキャラクター、ストーリーといった創作物を指す言葉として広く使われていますが、それぞれが必ずしも法的に保護されるとは限りません。 とくに「キャラクターの設定」や「物語のアイディア」のような要素は、著作権の対象にならないこともあります。 この違いを知らずに進めてしまうと、後々トラブルにつながることもあるので、どこまでが守られて、どこからがそうでないのかを見極める視点は欠かせません。
IP(Intellectual Property)の定義と略語の意味
IPは「Intellectual Property(インテレクチュアル・プロパティ)」の略で、日本語では「知的財産」と訳されます。これは法律的な用語であり、次のような範囲を含みます。
- 著作権(ゲーム、映画、音楽、マンガなどの創作物)
- 商標権(キャラクターのロゴや名前など)
- 意匠権(デザイン)
- 特許権(技術)
ただし、ゲーム・アニメ・漫画・映画などのエンタメ業界では、より広義に「ブランドやキャラクターそのもの」を指す言葉として使われています。

「IP(知的財産)」という言葉は、本来、著作権や特許などの法律で守られる権利を指します。 たとえば、キャラクターや物語などの創作物には、作られた瞬間から著作権が自動的に発生し、手続きをしなくても保護の対象になります。 ただ、ゲーム業界ではこの言葉がもう少し広い意味で使われていて、作品のブランドやシリーズ全体の“経済的な価値”を指すことも少なくありません。 法律的な定義とビジネス上の使い方にはズレがあるので、その違いを知っておくことはとても大事です。
ビジネス用語としてのIPの使われ方
ビジネス用語としての「IP(Intellectual Property/知的財産)」は、単に法的な権利を指すだけでなく、企業の収益源となる価値ある“資産”として扱われています。特にゲーム・アニメ・映画といったエンタメ業界では、「IP=キャラクターや作品ブランドそのもの」を意味することが一般的です。
たとえば、人気のゲームキャラクターやアニメ作品が、スマートフォンアプリ、グッズ、映像配信、さらには他社とのコラボレーションなど、さまざまな形で展開されているのは、そのIPの経済的価値を最大化するビジネス戦略の一環です。
こうした取り組みは「IP展開」「IP戦略」などと呼ばれ、1つの作品から複数の収益源を作る“メディアミックス”型のビジネスモデルとして、業界で広く活用されています。
また、企業によっては人気のあるIPを外部から取得し、自社コンテンツやサービスに組み込むことで集客力やブランド力を高める「IPコラボ」や「IP買収」といった動きも活発です。これは、ファンのついた作品を活用することで、自社のマーケティングや売上に直結する成果を狙えるためです。
このように、ビジネスの現場で「IP」は、「単なる権利」ではなく、「活かすべき価値あるブランド資産」としての意味合いで使われています。

ビジネスの現場では、「IP」という言葉が法律の枠を超えて、ブランドやコンテンツの価値そのものを指すようになっています。 たとえば「IP展開」や「IPコラボ」といった場面では、見た目は華やかでも、実際は著作権や商標、契約まわりの整理が欠かせません。 IPを“資産”として活かすには、その裏にある権利の持ち主や使い方のルールをきちんと確認しておくことが大前提です。 法律の視点とビジネスの視点、どちらか一方ではなく、両方を行き来できる目線がIP活用には求められます。
ゲーム業界における「IP」の意味と重要性

ゲームIPとは?キャラクター・世界観・作品ブランドの総称
ゲームIP(インテレクチュアル・プロパティ/知的財産)とは、キャラクター、ストーリー、世界観、ブランドなど、一つの作品を象徴し、ファンから認知される要素のすべてを指します。
たとえば、「マリオ」や「ポケモン」は、ゲーム本体だけでなく、マリオやピカチュウというキャラクター、彼らが生きる世界、さらにその影響力までも含んだIPです。ユーザーは単にゲームを購入するのではなく、そのIPの世界や体験に参加するライセンスを得ることになります。

「ゲームIP」といえば、キャラクターやストーリー、世界観などいろいろな要素が含まれますが、そのすべてが法律で守られているわけではありません。 たとえば、キャラクターの設定や世界観のざっくりした構造は、著作権ではなく“アイディア”として扱われ、保護の対象外になることもあります。 また、「人気」や「影響力」といった価値は、そもそも創作物ではないため、法律の枠ではカバーできません。 だからこそ、どの部分が守られていて、どこがそうでないのか。その違いをきちんと見極めて扱うことが大切です。
IPコンテンツとしてのゲームの特徴
ゲームIPは以下のような特徴を持つ強力なビジネス資産です。
ファンとの強い関係を築く
キャラクターや世界観に愛着を持つことで、ファンは熱狂的な支持者となり、ゲーム以外のグッズや関連商品にもお金を使うようになります。
メディアミックス展開が可能
アニメ化や映画化、グッズ、リアルイベントなど、異なるメディアと組み合わせてIPの世界を幅広く広げる仕組みが成立します。「ポケモン」や「妖怪ウォッチ」はアニメ化によって新たなファン層を獲得しました。
収益の多角化と長期化
ゲーム販売だけでなく、ライセンス収入、関連グッズ、イベント、海外展開などを通じて、一つのIPが継続的に利益を生む構造が構築できます。

「ゲームIP」といえば、キャラクターやストーリー、世界観などいろいろな要素が含まれますが、そのすべてが法律で守られているわけではありません。 たとえば、キャラクターの設定や世界観のざっくりした構造は、著作権ではなく“アイディア”として扱われ、保護の対象外になることもあります。 また、「人気」や「影響力」といった価値は、そもそも創作物ではないため、法律の枠ではカバーできません。 だからこそ、どの部分が守られていて、どこがそうでないのか。その違いをきちんと見極めて扱うことが大切です。
ゲームの「IP化」とは何を意味するのか?
「IP化」とは、ゲームとしてリリースされたコンテンツを、次のように様々なメディアや商品へと展開し、多面的なエンタテインメントに発展させるプロセスのことです。
アニメ化
代表例として「マリオ」「妖怪ウォッチ」「逆転裁判」などがアニメ化され、ゲームに触れない層へリーチできています。
グッズ展開
フィギュア、文房具、キャラクターくじの賞品やクレーンゲームのプライズ景品など、関連商品が大量に市場に出ることで収益源とファンエンゲージメントが強化されます。
リアルイベント・ライブ
ゲームキャラのコンサートやテーマパーク、2.5次元舞台など、リアル体験としての価値を発信します。

「IP化」という言葉は、つい商品展開やアニメ化といったメディア展開のことだと思われがちですが、本来はもっと広い意味があります。 それは、IPを別の文脈に置き直して、新しい価値を生み出していくプロセスのこと。 アニメやグッズ、イベントなども、ただ派生させるのではなく、作品の世界観や体験を“どう届け直すか”がカギになります。 こうした展開を通して、ファンがIPに触れる場が増え、体験を共有する機会も広がっていきます。 単に広げるだけでなく、どう“育てていくか”。その目線が、これからのIP活用ではますます重要になっていきます。
人気ゲームIPの具体例と成功戦略

任天堂のIP戦略と強さの秘密
任天堂は「マリオ」「ポケモン」「ゼルダの伝説」「星のカービィ」といった世界的に支持されるIP(知的財産)を軸に、多角的かつ緻密なIP戦略を展開しています。その核となる3つのポイントをご紹介します。
ポケモン(Pokémon)
1996年の登場以来、破竹の勢いで人気のポケモン。ゲームだけにとどまらず、アニメ・映画・トレーディングカード・グッズなどの“メディアミックス”を実践。一つの世界観をさまざまな形で提供し続けることで、あらゆる年齢層に訴求し続けています。
マリオ(Mario)
「スーパーマリオブラザーズ」から続くプラットフォーム系ゲームを中心に、全世界での知名度を誇る超人気IP。マリオは「マリオカート」シリーズ、「マリオパーティ」シリーズなどスピンオフタイトルにも展開され、さらに映画(「ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー」)、テーマパーク(ユニバーサル・スタジオの「スーパー・ニンテンドー・ワールド」)まで手がけることで、遊び方や体験の幅を広げています。これは「IPに触れる人口の拡大」を重視する任天堂の基本戦略と一致します。
ゼルダの伝説(The Legend of Zelda)
1986年の初代から長く愛され続け、最新作「Tears of the Kingdom」も世界的ヒット。ゲーム本体での高評価に加え、実写映画化計画も進行中で、「マリオ」映画の成功を受けて新たな展開に注目が集まっています。一つのIPが世代を超えて「探検」「世界観」に対する没入体験を提供し続けることが、任天堂らしい強みです。

任天堂のIP戦略には、ただ人気作品を出して終わりにしない、“世代を超えて育てていく”という強い意識が感じられます。 マリオやポケモンのように、ゲームだけでなく映画やテーマパーク、グッズなどともつなげていくことで、日常の中にIPと出会う場面がどんどん増えていきます。 特に「ゼルダの伝説」に見られるような、深く入り込める体験づくりは、単なる商品展開ではなく、“世界とつながる感覚”をユーザーと共有しているように思えます。 IPは繰り返し使うものではなく、そのたびに“読み直し”や“体験し直し”を通じて深まっていくもの。任天堂の取り組みは、それをよく表しています。
バンダイナムコの代表的IP一覧とその展開
バンダイナムコは、独自のIP軸戦略を通じて、ゲーム・アニメ・グッズ・イベントなどへ多面的に展開し、IPの価値を最大化しています。
ガンダム(Mobile Suit Gundam)
ガンダムは1979年のアニメ放送開始以来、日本発のロボットIPとして圧倒的な存在感を持ち続けています。ゲームやアニメの本編以外にも、プラモデル(ガンプラ)を中心に据えたIP展開が特徴的です。プラモデルの生産は年々拡大しており、静岡の新工場による生産能力強化にもつながっています。さらに米国に実写映画製作子会社を設立し、海外市場への展開も加速中です。このようにIPとしてのガンダムは、模型、映像、映画、イベントといった多角的軸で構成され、ファン層や地域を超えて強力に支持されています。
アイドルマスター(THE IDOLM@STER)
「アイドルマスター」は2005年にアーケードゲームとしてデビューして以来、重厚なメディアミックス展開で確固たるファン基盤を築きました。スマホアプリや家庭用ゲーム、アニメ、ライブイベント、ラジオ、CD、グッズなど、多彩なチャネルで継続的に盛り上がりを見せています。特にスマホアプリのリリースは初週ランキングトップとなる成功を収めており、これは企画力とファンコミュニティを活かしたIPの生命力を示す事例と言えます。
テイルズ(Talesシリーズ)
「テイルズ」シリーズは1995年に始まったロールプレイングゲーム(RPG)で、世界観や物語設計の深さが特徴です。バンダイナムコスタジオが主体となり、本編ゲームの制作を通じてIPを重厚に育てています。また「テイルズ オブ アライズ」など近年のタイトルには大型DLCやリマスター展開も取り入れられており、ライセンス展開によってファンとの接点をさらに強める戦略が進行中です。

■ ガンダム(Mobile Suit Gundam) ガンダムは、日本を代表するロボットIPとして長年にわたり圧倒的な存在感を放ち続けています。 アニメやゲームだけでなく、中心にあるのはやはり“ガンプラ”の展開。なかでも「モビルスーツバリエーション(MSV)」の取り組みは、本編には登場しない機体や設定を公式に広げるもので、ファンの想像力をかき立てながら世界観をどんどん広げていきました。 ガンプラとの連動を通じて、ガンダムIPが多層的に成長していったターニングポイントとも言えます。 ■ アイドルマスター(THE IDOLM@STER) 「アイドルマスター」はアーケードから始まり、スマホアプリや家庭用ゲーム、アニメ、ライブ、CD、グッズといった多彩な展開で、着実にファン層を広げてきたシリーズです。 特にライブイベントやSNSでのファンとの交流が、ただの“作品”ではなく“関係性”としてのIP価値を高める力になっています。 一方的に届けるのではなく、双方向のやりとりでファンと一緒に育ててきたことが、このIPの大きな強みです。 ■ テイルズ(Talesシリーズ) 「テイルズ」シリーズは、物語性の高いRPGとして知られ、ひとつひとつの作品が深い世界観とテーマを持っています。 本編を軸にしながら、近年はDLCやリマスター、アニメとの連携といった展開も加わり、作品世界に触れ続けられる機会が増えています。 ファンが長く付き合える土台がしっかり整っていることが、テイルズIPの育ち方を支えていると言えそうです。 こうして見てみると、バンダイナムコのIPはどれも“作品単体”で終わらず、いろんな接点や体験を通してファンと関係を築き、じっくり価値を積み上げているのが特徴です。
スクウェア・エニックスの代表的IP一覧とその展開
スクウェア・エニックスは、長年にわたって高い収益性とブランド力を維持している強力なIP群を持つ企業です。代表的なIPとして、「ドラゴンクエスト」「ファイナルファンタジー」「キングダム ハーツ」の3つを中心に紹介します。
ドラゴンクエスト(Dragon Quest)
「ドラゴンクエスト」は、スクウェア・エニックスが開発・発売する日本を代表するロールプレイングゲーム(RPG)シリーズです。1986年に第1作が発売されて以降、勇者が世界を救うという王道ファンタジーの物語や、ターン制バトル、レベルアップといったシンプルで親しみやすいゲーム性で、多くのファンに愛されてきました。キャラクターデザインは「ドラゴンボール」で知られる鳥山明氏、音楽はすぎやまこういち氏が手がけており、作品の世界観づくりに大きく貢献しています。シリーズはナンバリング作品のほかにもスピンオフや映画、アニメなど幅広く展開され、今なお高い人気を誇る国民的ゲームです。
ファイナルファンタジー(Final Fantasy)
「ファイナルファンタジー」は、1987年に登場して以来、全世界で一億本以上を売り上げる国際的RPGブランドです。近年では「Final Fantasy VII リメイク」が日本・北米・欧州での圧倒的な販売実績を記録しました。さらにNintendo Switch 2などマルチプラットフォームへの展開計画が進行中で、AAA (トリプル・エー)作品としてIPの継続的な強化を図っています。
キングダム ハーツ(Kingdom Hearts)
「キングダム ハーツ」は、スクウェア・エニックスとディズニーのコラボによるクロスオーバーRPGとして知られています。ゲームシリーズだけでなく、サウンドトラック・フィギュア・小説・カードゲームなど多様な関連商材展開が進んでおり、アニメやイベントでも高いファンエンゲージメントを維持しています。
IPビジネスにおけるゲームの役割と影響力

なぜ今、IPビジネスが重視されているのか?
ゲーム業界では、IP(知的財産)こそが企業の成長と競争力の源泉となっています。開発・配信コストは膨張する一方、市場は飽和状態。そんな中、オリジナルの強力なIPをもつことが「参入障壁」になり得るのです。
また、IPは単なる権利ではなく、ファンがキャラクターへ抱く愛着を通じてプレイヤーの定着を促す資産にもなります。ストーリーや世界観に共感したユーザーは、グッズ購入や続編購入など、自然と消費行動につながります。
さらに、外部IPの活用(ライセンス取得)は、集客や認知拡大を狙ううえで即効性のあるマーケティング手段として効果的です。たとえば、欧米で人気になり収益が好調である「モノポリーGo!」など、既存IPを組み込むことでユーザー獲得コストを下げつつ安定収益を担保する事例が報告されています。

ゲーム業界では、IPをどう活かせるかが企業の強みを決める大きなポイントになっています。 なかでも外部IPを使う場合は、「そのIPを託してもらえる信頼」と、「決して小さくないライセンス料」が必要になるため、そもそも参入自体にハードルがあります。 だからこそ、実績やブランドなど、IPの持ち主から“任せたい”と思ってもらえる関係づくりが欠かせません。 そしてIPは、ただの権利ではなく、ユーザーとのつながりを深めてくれる“ブランド資産”でもあります。 外部IPを使った展開は、短期間で注目を集めたいときに効果的ですが、それを活かすには丁寧な姿勢と、ちゃんと伝える工夫が必要です。 これからは「どう使うか」ではなく、「どう育てて、どう届けるか」という目線がより問われていくはずです。
自社IP・他社IPの違いとメリット
自社IP(オリジナルIP)
自社IPはゼロから創り上げる権利であり、「キャラクター」「デザイン」「世界観」などを自分たちのペースで自由に設計できます。自社で権利を完全保持するため、ライセンス料などのロイヤリティを気にせず、グッズやアニメ、ゲームなど複数の展開において利益が自社のものとして最大化されます。さらに、DLC(ダウンロードコンテンツ)や映画など後続展開を見据えた戦略が立てやすく、成功すれば長期間にわたる収益基盤となるのがメリットです。
他社IP(ライセンスIP)
他社が保有するIPを借りるライセンス形式では、“既に人気のあるブランドやキャラクター”がすぐに使えるため、開発初期段階からマーケティング効果が高く、集客しやすいメリットがあります。既存ファンによる自然なユーザー獲得や広告コストの削減に効果的で、市場への即応力が魅力です。ただし、ロイヤリティの支払い、契約条件、使用範囲などに縛られ、自由度は制限される点には注意が必要です。

IPを活用するには、大きく分けて「自分で育てるか」「借りて使うか」という選択があります。 自社IPは自由度が高く、うまく育てば長期的な資産にもなりますが、そのぶん立ち上げには時間もコストもかかります。 一方で、他社IPはすでに人気や知名度がある分、短期間で成果を出しやすい反面、契約の条件や使用範囲などに縛りが出やすくなります。 最近では、自社IPをじっくり育てていくスタイルが重視される傾向もあり、どちらを選ぶかは自社のフェーズやリソースとのバランス次第。 大事なのは、「どのIPを、いつ、どう使うか」を見極めて、ちゃんと戦略として組み立てることです。
新規IP開発の挑戦と重要性
新規IPの開発はリスクを伴いますが、成功すれば企業にとって大きな財産となります。新たなブランドを創出し、長期成長を見込める点が魅力ですが、同時に次のような課題にも取り組む必要があります。
世界観やキャラクター設計の構築
独自性と魅力を兼ね備えたストーリーや人物像がファン定着の鍵となります。
法務や権利整備の徹底
商標や著作権をはじめ、使用範囲や侵害リスクを未然に防ぐ環境整備が肝心です。
メディアミックス展開戦略の策定
ゲームだけでなく、続編DLC(ダウンロードコンテンツ)、アニメ化、グッズ展開などを想定した多面的な展開計画が効果を高めます。
ファンとの強い結びつきを生むUX設計
“このキャラが好き”“この世界に浸りたい”という想いを育む演出や体験が、継続課金や口コミを生みます。
新規IP開発には多くの努力とリスクが伴いますが、成功すれば数年、数十年と事業を支える知的財産の柱になる可能性を秘めており、企業にとって極めて価値の高い取り組みです。

新しいIPをつくるのは、決して簡単なことではありません。でも、そのぶん大きなやりがいがあります。 大事なのは、ただ“作って終わり”にせず、どう育てていくかをちゃんと考えること。 魅力的なキャラクターや世界観をしっかり作り込んで、「もっとこの世界に触れていたい」と思える体験を届けられたら、自然とファンはついてきます。 それに、著作権や商標といった権利まわりの準備が整っていれば、そのあとの展開もスムーズに進みます。 時間はかかっても、丁寧に育てたIPは、きっと長く企業の力になってくれるはずです。 焦らず、一歩ずつ価値を積み上げていく姿勢が、何より大切だと思います。
IPを活かしたゲーム戦略とは?開発・マーケティングの視点から解説

スマホゲームやソシャゲにおけるIPの効果
スマホゲーム/ソーシャルゲーム(ソシャゲ)において、人気IPを使うことでマーケティングコストや獲得効率を大幅に改善できます。既に知名度やファン層があるIPを採用することで、広告費を抑えてDL数を伸ばす利点があります。
さらに、IPとのコラボイベントや限定キャラ追加などでファンのエンゲージメントを高め、課金額を増加させる効果も見込めます。アニメIPを取り込んだゲームアプリがこれに該当します。
アニメ・バラエティ・他メディアとのクロス展開
ゲームIPはアニメ、映画、グッズ、イベントなどのクロスメディア展開を通じて、ブランドの認知力と収益性を強化します。「マリオ」の映画や「ポケモン」のアニメ化などが典型例です。
また、アニメ原作ゲームやタイアップコラボは、相互広告・導線効果が高く、ファンが異なるメディアに渡って追いかける強力なリテンション効果を生みます。
人気IPを活用したゲームのメリット
強力な集客力
人気IPの知名度・ブランド力を借りることで、リリース直後から注目を集める効果があります。既存ファン層へのアプローチが容易になり、広告費の効率が改善します。
マーケティング上の優位性
有名IPを冠することで、広告クリック率やPV数が向上する可能性が上がります。ユーザーは「好きなキャラが登場するなら試してみよう」と感じやすいため、立ち上げ時点でのユーザー獲得がスムーズになります。
ファンとのエンゲージメント強化
IPキャラの追加、コラボイベント、限定スキンなどにより、ファンは継続的に課金しやすくなり、リテンション率も高まります。既存ストーリーへの愛着をゲーム内で体験し、長期プレイに繋がります。
開発・プロモーションの効率化
世界観やキャラ設定など膨大な世界構築が不要になるため、制作コストや開発期間を節約でき、IPに既存資産がある分、企画検討や素材制作にかける時間を短縮できます。
クロスメディア展開の土台
アニメ化、映画化、グッズ化など、多方面に渡る展開がしやすく、メディアミックスによる収益多角化が可能です。ゲーム内での成功が他媒体への流入を生む良循環も期待できます。
IPを活用したゲームのデメリット
ライセンス料と収益負担
他社IPを使う際は、売上の5%前後のロイヤリティがかかるのが一般的です。これが高コストとなり、利益率に影響します。
制作の自由度の制限に関する問題
IP所有者の意向に沿ってキャラの特徴や世界観を忠実再現する必要があり、独自性の高い企画やゲーム性の変更が難しいことがあります。
契約や承認のハードル
制作工程ごとに何度も承認を得る必要があり、コミュニケーションの遅れや条件変更が発生しやすいです。承認者が多いと開発スピードが低下し、マネージメントの負担が大きくなります。
ジャンルとの相性ミスマッチ
IPとゲームジャンルやメカニクス(ゲームのルールやシステム、プレイヤーの行動や操作など)が噛み合わないと、ファンに刺さらず支持されないケースがあります。
寿命短期化リスク
IP人気が下火になるとともに売上への依存度が高いゲームは短命化しやすく、知名度の下落に従って廃れるため、市場での持続性が損なわれる危険があります。

人気IPを使ったゲームづくりは、ユーザーに短期間で届きやすく、かなり効果的な戦略のひとつです。 よく知られたキャラクターや世界観は、それだけで話題になりやすく、特にスマホゲームのようなスピード感のある市場では大きな強みになります。 ただその一方で、ライセンス費用がかかったり、制作まわりの自由度が下がったりと、避けられない課題もあります。 だからこそ大切なのは、IPの魅力をしっかり理解したうえで、ゲームのジャンルや体験内容とちゃんと噛み合うように設計すること。 ユーザーにとって“遊びたい”“続けたい”と思える体験をどうつくるかがポイントです。 IPを「借りる」だけで満足せず、どう「活かして、育てていくか」が、これからますます問われていくと思います。
IPを扱うゲーム業界で働くには?転職のヒント

IPを扱う代表的な企業情報まとめ
任天堂
任天堂は、「マリオ」「ポケモン」「ゼルダの伝説」など世界的に人気のIPを多数保有する企業です。特に電子商材に加えて、スマホアプリ、テーマパーク、映像コンテンツなどマルチメディア展開を進めていることが特徴です。
採用面では、ゲーム開発エンジニア、スマートデバイス向けアプリエンジニア、ネットワークエンジニア、知的財産関連職など多様な専門職の求人が存在します。
特に知的財産部では、自社IPを守る法律文書の読解・契約処理・社内外折衝が求められ、グローバルなコミュニケーション力や文章力が重要視されています。
任天堂は中途採用に関して約3割超の採用比率であり、即戦力が求められる一方、企業文化へのフィットや「任天堂DNA(独創性・誠実さ・柔軟性)」を体現できる人材が転職成功しやすいとされています。
バンダイナムコ
バンダイナムコは、「ガンダム」「アイドルマスター」「テイルズ」などの強力IPを持ち、ゲームからアニメ、ライブ、グッズまでの一貫した展開を行う企業グループです。
同社ではゲームプロデューサー/プランナー、マーケティングディレクター、テクニカルディレクター、UXデザイナー、ライセンス管理者など、多彩な職種がキャリア採用されています。
特に「IPエンハンスプロデューサー」などの役割は、ファン体験の設計・イベント企画・版権元との折衝など を担い、“ファンと一緒にIPを育てる”役割として注目されています。
また、「バンダイナムコID」のようなグループ共通プラットフォームの開発・運営担当もおり、技術者としてIP軸戦略推進に貢献できます。
スクウェア・エニックス
「ドラゴンクエスト」「ファイナルファンタジー」「キングダム ハーツ」などのIPを展開するスクエアエニックスでは、プランナー、プロデューサー、エンジニア、CGクリエイター、ローカライズ担当などが募集されています。
また、出版関連のIP活用担当(グッズ企画・イベント運営等)も活躍の場が多く、求人では合同会社の出版用イベント・グッズ制作担当職なども募集されています。ゲーム本編以外にも出版・メディアミックス領域でのキャリア構築が可能な点も魅力です。
なお、同社への転職は難易度が高く、実績と創造性や業務遂行能力をしっかり示す必要があります。

IPビジネスに関わるゲーム会社への転職を考えるなら、「どんなIPに関わりたいか」だけじゃなくて、「そのIPをどう育てて、どう届けたいか」という視点も持っておきたいところです。 任天堂やバンダイナムコ、スクウェア・エニックスなどの大手各社は、それぞれに独自のIP戦略を持っていて、関われる職種も本当に幅広いです。 最近では、ゲーム開発にとどまらず、イベント、グッズ、プラットフォームの運営など、IPの活かし方がどんどん広がっています。 転職を目指すときは、自分のスキルがIPのどこで活きるのかを見極めると同時に、「どうやってユーザーとつながるか」という発想もすごく大切です。 単に「ゲームを作る」ではなく、「体験を届ける」という意識があるかどうか。そこが活躍できるかどうかの分かれ道になると思います。
IPビジネスに関わる職種とスキルセット
プロデューサー
IP付きプロジェクト全体を統括。スケジュール・予算・クオリティ管理、社内外の調整、ライセンス契約の実務経験が必要です。外部との折衝力や判断力が問われます。
ゲームプランナー
ゲーム企画の中核。IPの魅力を活かすシナリオ構成や機能設計を行う。人気キャラや世界観を新機能に落とし込む企画力とドキュメント作成力が求められます 。
マーケター
IPファンに向けたプロモーション戦略を立案。広告、SNS、キャンペーン企画、ファンコミュニティ運営など、IPごとのターゲット特性を理解しながら運用していく技術が必要です。
ライセンス管理
IP使用に関する契約交渉・承認・権利管理を担当。対外折衝・契約スキル・法務知識が求められ、任天堂やバンダイナムコのような大手企業では専任部署もあります。

IPビジネスに関わる仕事は、いろんな人との連携や、ファンへの深い理解が求められるぶん、大きなやりがいのある領域です。 たとえばプロデューサーは、全体を引っ張る旗振り役として、調整力や判断力が問われます。 プランナーなら、IPの魅力をどう新しい遊びに落とし込むか、創造力がカギになります。 マーケターはファンの気持ちに寄り添いながら、「どう伝えるか」を日々考え続ける仕事です。 ライセンス管理は表には出にくいですが、契約や交渉を通してIPの価値を守る、大切なポジションです。 どの職種にも共通しているのは、IPを“素材”としてではなく、“ブランド”としてしっかり向き合う姿勢。 好きなIPを「届けたい」「育てたい」と思っている人にとっては、とても魅力的なフィールドだと思います。
IP業界志望者のためのポートフォリオ・志望動機の書き方
ポートフォリオ
IPファンに刺さる企画やビジュアル、プレゼン資料を準備することが大切。たとえば「マリオをテーマとしたゲーム企画書」や、「FFキャラ活用の広告案」など、IP活用策をアウトプットにして見せると効果的です。
志望動機
「なぜそのIPなのか」「自分ならどんな価値を加えられるか」を語ることが重要です。単に「ファンだから」ではなく、「○○の世界観をこう使って拡張したい」「ファンコミュニティと一緒に育てたい」など、具体的に語り、戦略性と熱意を示しましょう。

IP業界を目指す人にとって、ポートフォリオや志望動機は“熱意”と“理解力”を伝えるための大事な道具です。 ポートフォリオでは、好きなIPをどう活かしたいのかを具体的に見せることで、その人なりのアイデアの方向性や、ユーザーに対する理解の深さがしっかり伝わります。 オリジナルの提案であっても、「このIPだからこそできる体験」が描かれていれば、それだけで強い説得力になります。 志望動機も同じで、単に「この作品が好きです」だけでは足りません。 「自分のスキルや視点で、何をどう提供できるのか」を言葉にして伝えることが、共創パートナーとしての魅力につながっていきます。 IPは“使うもの”ではなく、“育てていく存在”です。 その姿勢を、自分の言葉でちゃんと表現できるかどうかが、選考で差がつくポイントになってきます。
IPビジネスに関するよくある質問

Q:ゲーム業界で「IP」とは何の略?
ゲーム業界における「IP」は Intellectual Property(知的財産) の略です。これは単なる商標やキャラクターだけでなく、「キャラクター」「世界観」「物語」「アートワーク」など、創作されたコンテンツそのものを指します。つまり、ゲーム会社にとって「マリオ」「ポケモン」のような人気作品=IPは、企業の大きな資産(アセット)なのです。
Q:自社IPと他社IPの違いとは?
自社IPとは、自社で企画・制作し、権利を全て所有するIPのこと。自社IPは自由度が高く、収益や意思決定も自社に帰属しますが、開発には高コストと長期間の投資が必要です。
一方の他社IPは、他の企業やクリエイターが所有するIPをライセンス契約により使用するもの。人気既存ブランドを利用できる即効性の強みがある一方、ライセンス料が発生し、制作内容にも制約がある点には注意が必要です。
Q:IPがあるとゲームは売れやすい?
IPを活用したゲームは、ファンの信頼・認知力・エンゲージメントを得やすく、リリース直後から集客力が高まります。さらにキャラクターや物語を活かしたコラボやイベントで課金率や継続率も向上しやすいです。ただし、IPへの依存が強すぎると自由な企画が難しくなる、ライセンス料が利益を圧迫するリスクもあります。
Q:IPビジネスの将来性は?
IPビジネスは今後、ますます成長が期待される分野です。ゲームやアニメ、映画、グッズ、イベントなど多様なメディアへの展開が続き、感情と記憶を結ぶ「共感資産」としての価値が重視されます。
また、メタバースやNFTなどの新技術との掛け合わせにより、ファンが主体的にIPを所有・体験する次世代の展開モデルも進行中で、IP人材への需要は高まり続けています。

ゲーム業界でよく耳にする「IP」という言葉、本来は「知的財産(Intellectual Property)」という法律用語です。 でも最近では、キャラクターや世界観といった“作品そのものの価値”を指す言葉として、少し広めの意味で使われることも増えてきました。 よく「IPがあればゲームは売れる」と言われることもありますが、実際にはそれだけで成功が決まるわけではありません。 長く愛されるためには、IPの魅力をちゃんと活かした企画づくりや、ファンが楽しみ続けたくなる工夫が欠かせません。 これからのIPビジネスは、メタバースやNFTなど新しい技術との組み合わせも注目されていますが、ただ広げるだけではうまくいきません。 大切なのは、権利をきちんと守りながら、ファンとの信頼関係をコツコツ築いていくこと。 「持っていること」よりも、「どう育てて、どう活かしていくか」。今は、そんな時代に入ってきていると思います。
IPとは「資産」であり「物語」。ゲーム業界の未来を支える核になる!ゲーム業界への転職なら株式会社ヴィジョナリー
IPは単なる商標やキャラクターではありません。感情、記憶、物語に基づく“共感資産”であり、それをゲーム化・体験化できる人材は、業界で強く求められます。今後のゲーム業界は「IP × 体験価値」へとシフトし、IPを理解し、活かすスキルがキャリアを左右する時代です。
IPを扱うゲーム業界、エンタメ業界への転職をお考えなら、株式会社ヴィジョナリーのサポートをご活用ください。IP業界に精通したエージェントが在籍し、ポートフォリオの設計アドバイスや志望動機の構築も丁寧にサポート。未経験や業界チェンジの相談にも対応し、IP理解の深掘りやキャリアマップを一緒に描きます。
「IPビジネスを支える人材」としての価値を高めたい方は、ぜひ一度ヴィジョナリーの無料面談をご利用ください。

IPは、ただのキャラクターや名前ではありません。 そこにある物語や世界観、そしてファンとの感情的なつながりまで含めて、"共感資産"としての価値がとても大きいんです。 それをゲームという体験に落とし込める力は、これからのエンタメ業界でますます重視されていくはずです。 IPを軸にキャリアを築きたいと考えている人にとっては、自分の強みや興味をどう活かせるかをしっかり言葉にすることが大切になります。 単に「この作品が好きだから」だけでなく、「どんな風に届けたいのか」「どうやってその価値を広げていきたいのか」。 そんな視点を持って伝えられたら、志望の説得力もぐっと増してくると思います。

.webp)
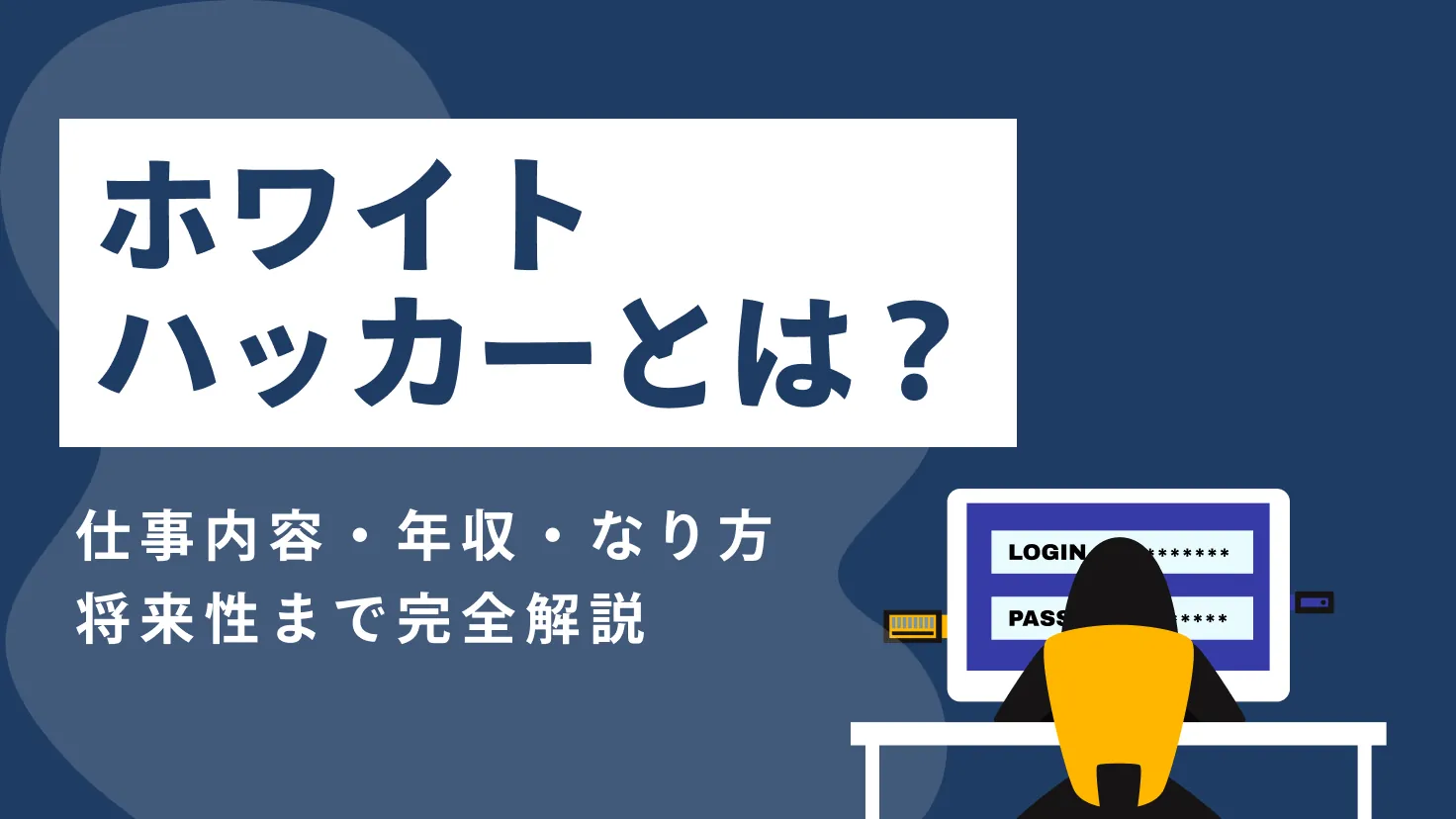
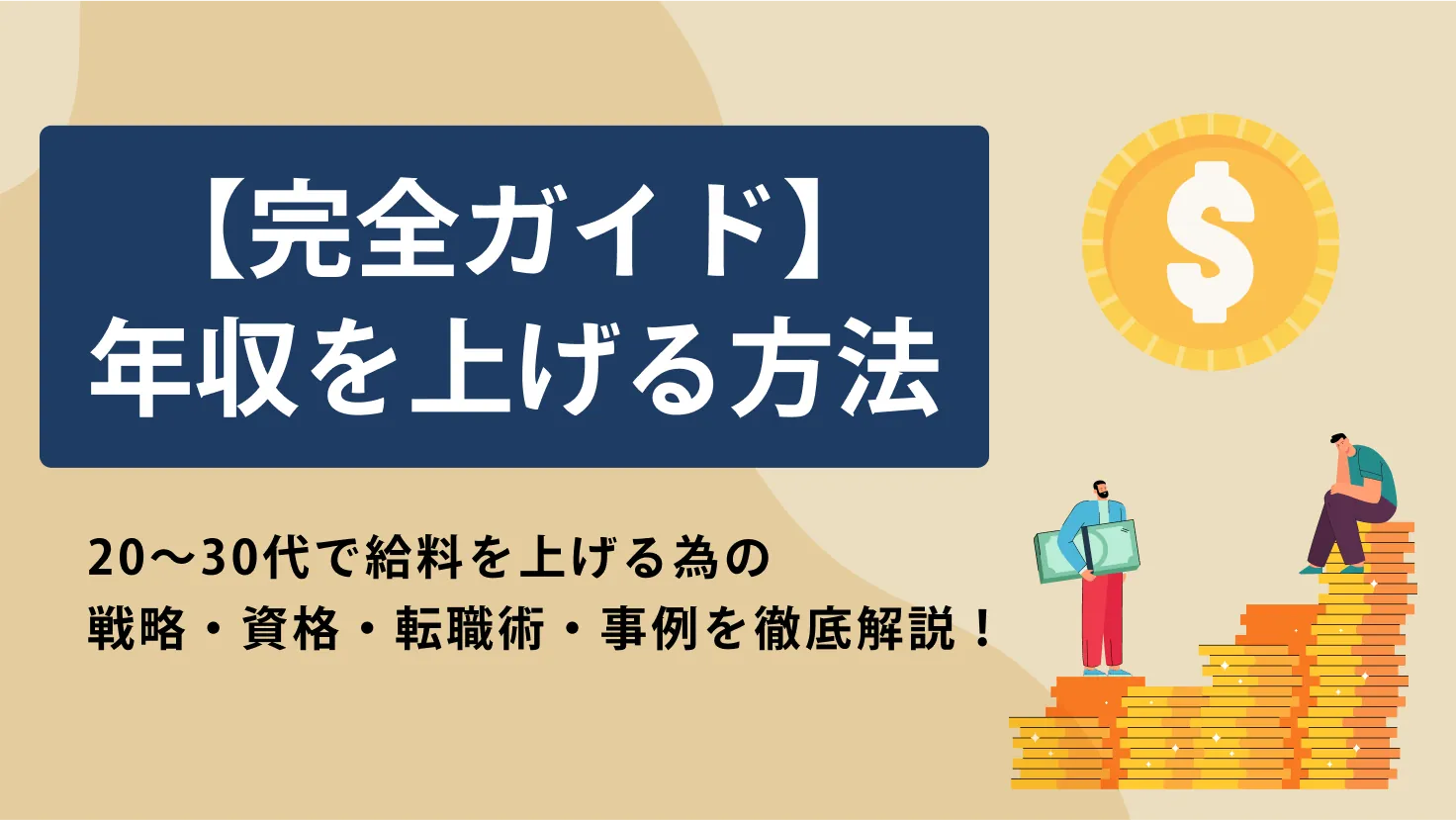

.webp)

.webp)
.webp)